今朝の検温

平熱です。
わざと?(゜゜)わかってない?ショーバイだから?
世のなかには「霊符(護符)」とよばれるおまじないのお札があります。
以前これについて書いた記事がアクセス数を稼いでくれており、たいへんありがたいのですが、ときおり(開示していませんが)コメントもいただきます。
べつにこれでご飯を食っているわけでもないのに質問がくるのも不思議だとおもっていたのですが、教えられた霊符(護符)の通販サイトを眺めていて、なにが質問の趣旨か理解しました。
商売人には答えられないはずです。まじめに返答すれば、商売の根底がひっくり返りかねません。だから、これで商売していない私のような者のところに、質問が来るのですね……。
どうもこれはいけません。
訴えられたら困るし露骨に書けないため自分でもまどろっこしい書きかたになっていますが、ご了承ください。
たとえば「大招官職符」と俗称されている霊符(護符)があります。
「この符、官職を大いに招く」とあり、所持し、屋敷に祀ることで仕事がうまくいき、天職にありついて転職もスムーズになるとされます。まず、これが「道蔵」という5世紀に成立した(とされる)書物に載っている図柄です。
大正時代に刊行された「鎮宅霊符神」という本に伝わる図柄です。この本は大阪の妙法寺におられた山岸乾順(金華山人)師によるものですので、仏教系寺院に代々伝わって来たものといえるでしょう。
これは大阪府交野市の星田妙見宮のホームページにある「大招官職符」です。
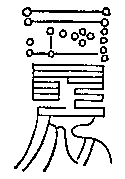
以前、八代妙見宮の「太上神仙鎮宅霊符」の掛け軸を撮影し、後日、整理するため書き起こして保存していたのがこれで、ほとんどかわりません。神社(妙見宮)系列は、どうやらこの図柄で伝承されてきたことがわかります。
つまり「大招官職符」といっても、すくなくとも3系統の図柄があります。
問題は、この「大招官職符」の名前を少し変えて(招官職符とか)、複数種類の微妙に効用がことなるものとして頒布している霊能者?ショーバイニン?のサイトがあることです。
すこし調べれば中国に伝わる原書(とされるもの)、仏教系、神社系で、代々時代を経ていくにつれて食い違っていっただけのものとわかるのに、3種類、似たような名前で似た効用の別のお札がある、ぜんぶ買うと効果絶大ですよ?みたいな商売って、どうなんでしょうか。
しかもこれ、墨をすって和紙に書くだけなのに、一枚8,000円とか……。
祈祷料込みだといわれたらなんともいえませんが、ほんとうに斎戒沐浴して吉日をえらんで深夜に祈祷してからまじめに書いてたら、量産どころじゃありません。「道蔵」で「聖降日」とされるのは年12日しかありません。次善としてこれに亥・卯・酉の日をくわえても、年半分届きません。
そもそも、やたら大自然の中で修業しながら書いていますみたいな写真載せているのに、通販サイトである以上かならず記載しないといけない「販売主体についての表示」にある住所をgoogleマップで検索すると、都会のマンションだったりします。
どれが正しいかは私ごときがとやかく言うことではありませんが、どれもそれぞれに歴史があるものですから、深く考えずデザインの気に入ったものをえらぶようおススメしています。


